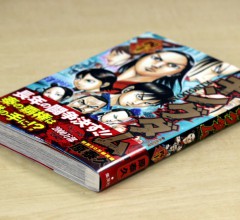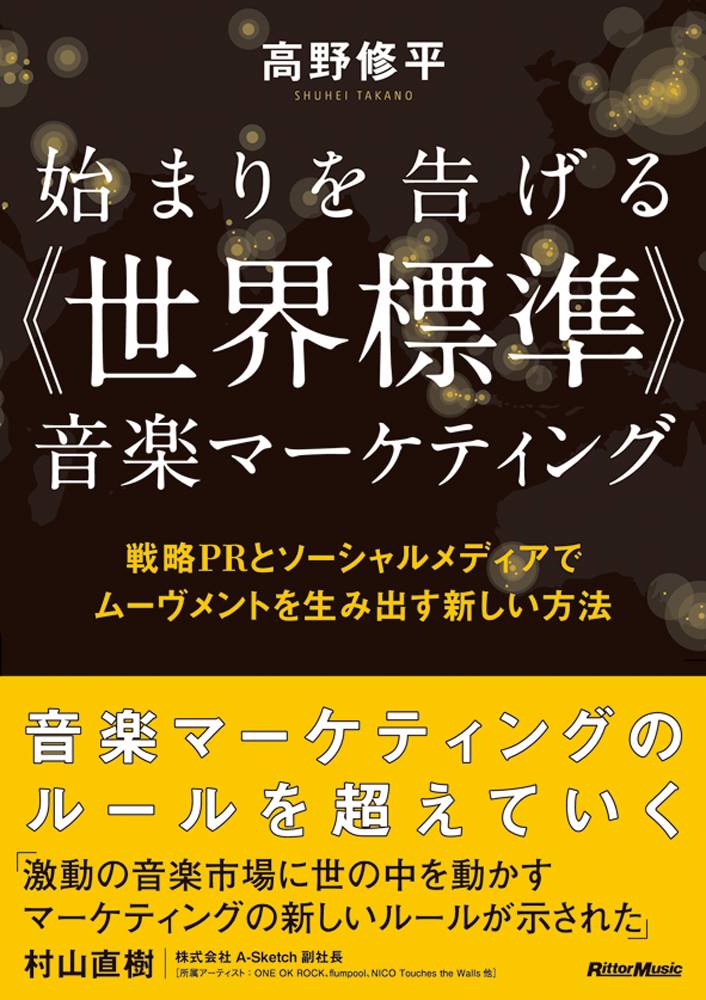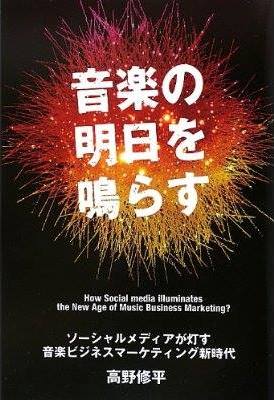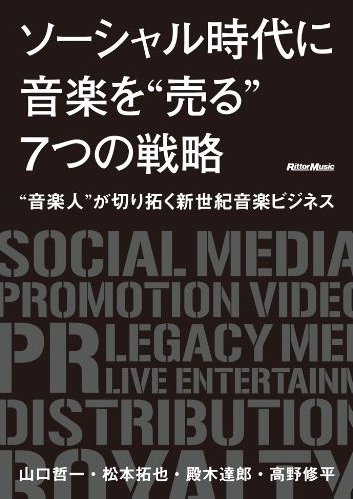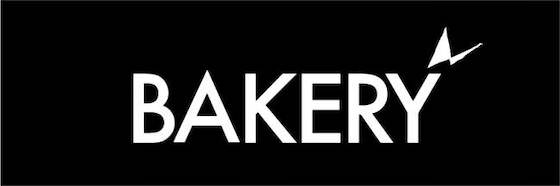「Netflix」が2015年9月2日に日本でもローンチしました。2015年は映像や音楽における「サブスクリプションサービス元年」ともいえる年になったと思います。
映像や音楽は、マーケティングテクノロジーの進化も含め、デジタルへの移行が進んでいます。これはネット環境やデバイスの発達によりテクノロジーが生活の中心へと融合されていく中では不可逆の流れです。
その中で、今回Netflixがローンチした前後の展開を見ていくと、今の時代にマッチしたマーケティングの手法が見て取れます。今回は、Netflixのマーケティング戦術を分析してみます。
見放題も月額料金も訴求しないNetflix
一般的なデジタルサブスクリプションサービスのマーケティングメッセージはおおむねどこもこれに限られます。それは「見放題と価格を全面に押し出す」ことです。
「何万というコンテンツがこのサービスなら見放題です」
「費用は月額980円です」
しかし、残念ながらそのマーケティングメッセージでは刺さらないのが今の生活者です。その背景には多くの事象が複雑に絡んでおり、どれか1つだけが理由というわけではありませんが、いずれにしても「誰も見放題を求めていないし費用がお得だとも思っていない」というのが現実です。
ブランド側が売り出したいメッセージと生活者のニーズがマッチしていないといったパターンは、一般的なブランドがマーケティングを行う際にも同様に起きます。
例えば、研究に研究を重ねて開発した新機能がある製品に搭載されたとして、ブランド側はそれをマーケティングメッセージの中心軸に据えて展開しようとします。ところが実際世の中に出してみると、生活者の多くは新機能よりもカラーバリエーションの方に興味を持ってしまう。そんなことがよく起きます(何に対してであれ興味を持ってくれればまだましで、実際にはそこに行き着くまでが大変ですが)。
Netflixに話を戻しましょう。
もしもターゲットが膨大なカタログ数に価値を見いだすような映画オタクであれば、月額980円は安いと感じるでしょう。それならば、ターゲットとマーケティングメッセージは合致します。しかし、そうであっても今度は次の問題が発生します。
「競合の中からそのサービスが選ばれるべき理由はどこにあるのか?」
オリジナルコンテンツで差別化する
そこでNetflixは、数ある映像サブスクリプションサービスの中から選んでもらうために、オリジナルコンテンツを軸に「絞った」マーケティング戦略を展開します。
当たり前ですが、ブランドや商品をマーケティングする場合、担当者からすれば魅力的な要素は山程あります。「あれも言いたい。これも言いたい。あれも伝えたい。これも伝えたい」といった具合にです。
しかし、情報量が多すぎればかえって興味喚起を抱くべき点が伝わらなくなります。残念ながら生活者はそれらのメッセージの全てに耳を傾けているほど暇ではありません。
そこでNetflixは、「オリジナルコンテンツ」という軸に特化して全てのマーケティング戦略を描いています。
Netflixは膨大な映画やドラマをストックしていますが、主軸に据えたオリジナルコンテンツのラインアップは、ほぼ全てが「連続性」のあるものです。『Sense8』『デアデビル』『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』『テラスハウス』『アンダーウェア』など、どれも映画のように2時間で終わるものではなく連続性を持っています。
このようなコンテンツを軸にすることで、「定額見放題」というサブスクリプションサービスの特性が生きてきます。メリットは大きく分けて3つあります。
1つ目はシンプルに、コンテンツの連続性のため契約を持続してもらいやすいという点です。そしてこれは、多くのサブスクリプションサービスが展開している一定期間の無料視聴を有効なものにします。うまくハマってくれれば無料期間以後も課金してくれる可能性が高まるというわけです。
2つ目は、時間軸に依存しないオンデマンドのメリットをアピールできる点です。もちろんこれはNetflixに限ったことではありませんが、見逃しリスクがなくなることで、次回を見るモチベーションを失うということは格段に少なくなります。サービスを提供する側からいえば、地上波などでありがちな機会損失を防げるというわけです。

また、Netflixは日本で展開するに当たり、『テラスハウス』と『アンダーウェア』の2つのドラマを独自にスタートしていますが、こちらは毎週更新となっていた点にも要注目です。優れた海外ドラマには一度見始めるとやめられない魅力があり、『Sense8』や『デアデビル』『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』などの作品をシーズン丸ごと一気に見ることができるのは、それが好きな人には大いに歓迎されるでしょう。しかし、そもそも海外ドラマというジャンル自体をとっつきにくいものと考える日本人視聴者も少なくありません。そこで、日本独自のオリジナルコンテンツは一気に全部を出さず毎週更新とすることで、視聴の継続性を生み出し、アクティブ性を向上させる。これが3つ目のメリットです。
統一されたコンテクストを多彩な戦術で「面展開
さらにNetflixでは、生活者へのアテンション、興味喚起からコンバージョンまで、テレビCMやネット広告、イベントなどリアル/デジタルの垣根を超えて、オリジナルコンテンツという1つのコンテクストで訴求しています。そして秀逸なのは、コンテクストが1つでありながらも、ターゲティングは多彩な戦術で「面展開」されている点です。これは、ローンチ前後の動きを見るとよく分かります。
Netflixはまず、ネットリテラシーや映像などに関与度の高そうなアーリーアダプターをメインターゲットに据えました。ローンチ前からWeb PRを中心にマーケティングを展開し、アーリーアダプター層に対してオリジナルコンテンを中心でその魅力をアピールし、「いよいよNetflixが来るぞ」という期待感を醸成させたのです。
そして2015年9月1日、オリジナルコンテンツの出演者を海外からわざわざ呼び寄せ、アーリーアダプターやインフルエンサーをメインとした大規模なローンチパーティーを東京・六本木の国立新美術館で開催しました。このイベントはテレビを通じて大きく取り上げられましたので、その様子を目にした人も多いのではないでしょうか。
コンテクストが1つでありながらも、ターゲティングは多面的といったのは、まさにこれです。同じ1つのイベントが、リアルではアーリーアダプターやインフルエンサーをターゲットにしつつ、テレビを通じてはアーリーマジョリティやレイトマジョリティに対するPRとなっているというわけです。
また、このイベントでは出席者へのお土産として、Netflixが1年間視聴できるVIPパス1枚と半年間視聴可能なパス2枚を手渡すという施策を実施しています。アーリーアダプターやインフルエンサーのエンゲージメントをイベントで高め、その場からソーシャルメディアとマスメディアを活用した情報拡散を狙いつつ、さらにリアルでの「シェア」を促すことで、アーリーアダプターやインフルエンサーの周辺への拡散を狙っていたのです。
まさに一石二鳥。オリジナルコンテンツというコンテクストは変えずに、ターゲットごとにマッチしたマーケティング手法を駆使しているといえます。

Netflixの特性とマーケティング手法を合致させる
このように、Netflixはオリジナルコンテンツを軸にしながら、マーケティングメッセージとマーケティング手法をターゲットごとにしっかりと切り分け、展開しています。
この他にも芥川賞を受賞した又吉直樹の『火花』を独占映像化したり、ソフトバンクと組んでスマートフォンや光ファイバーサービスの加入者向けにサービスを訴求したり、テレビのリモコンに専用ボタンを搭載したりと話題が尽きないNetflixですが、その一つ一つをマーケティング的な視点から見ると、とても興味深いものがあります。
今回はNetflixのマーケティング手法を掘り下げてみました。まとめると以下のようになります。
- 戦略的なPRで世の中に空気を作る
- マーケティングメッセージを1つに絞る
- マス、デジタル、リアルのコンテクストを1つにする
- 一方で同じコンテクストの下でターゲティングごとにマーケティング手法を変える
一見しただけでは特に変わったところがないように見えて、実は綿密に計算されたコミュニケーションデザインといえます。これからNetflixがさらに何を仕掛けてくるのか、楽しみです。
この記事はITmediaにて連載中の「次世代エンタテインメントマーケティング」の第一回を転載したものです。最新記事は、「累計2000万部の大ヒットマンガ『キングダム』に学ぶ“高濃度シェア”の作り方」です。よろしければ御覧ください。